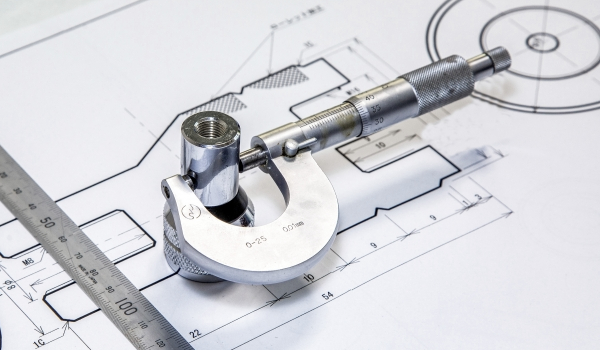技術コラム
鉄と鋼(はがね)のちがいって?特徴や材料規格について解説!

発行日:2025年10月24日
鉄と鋼(はがね)のちがい
「鉄」と「鋼(はがね)」という言葉はよく耳にしますが、「鉄と鋼って同じじゃないの?」と思ったことはありませんか?
実は、この二つにははっきりとした違いがあります。
製造業や機械設計に携わる技術者にとって、「鉄」と「鋼」は最も基本的な金属材料で、かつ最も奥深い素材です。両者の違いを正しく理解し、さらに鋼材の種類や特性を把握することは、最適な材料選定に直結します。
鉄は“素材”、鋼は“調整された鉄”
鉄(Fe)は、地球上に豊富に存在する金属で、純粋な鉄はやわらかく、延性がつよい反面、強度や耐久性には欠けます。
そこで鉄をベースに炭素をわずかに混ぜ、性質を変えたもの、それが「鋼」になります。炭素の含有量が0.02%〜2%程度の合金を「鋼」と呼び、それ以上になると「鋳鉄(ちゅうてつ)」になります。
つまり、鉄は“ベースになっている金属”、鋼は“鉄を改良、強化した合金”なのです。
鉄と鋼の呼ばれ方
純鉄(じゅんてつ)
純鉄は炭素やその他の不純物が非常に少ない鉄で、炭素含有量が0.02%程度までの鉄が一般的に純鉄と称されます。やわらかく、延性に優れますが、強度は低く構造材には不向き。主に電磁鋼板などの特殊な用途で電化製品、通信機器、産業機器に使用されます。
鋼(はがね)
鋼は、炭素含有量が0.02〜2%の範囲にある鉄合金です。炭素量により、以下のように分類されて呼ばれます。
・低炭素鋼(C:0.02〜0.25%)
… 延性・溶接性に優れ、強度は比較的低め。
・中炭素鋼(C:0.25〜0.6%)
… 強度と靱性のバランスが良く、構造材や機械部品に多用されます。
・高炭素鋼(C:0.6%〜)
… 比較的脆く、衝撃に弱いが硬度・耐摩耗性に優れ、工具やばねに使用されます。
鋳鉄(ちゅうてつ)
炭素含有量が約2%以上のものを鋳鉄といいます。硬く脆いですが、耐摩耗性に優れ鋳造性も高い材質です。工作機械のベッドやエンジンブロックに使用されています。
代表的な鋼材と規格
1. 一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101: SS材)
建築や橋梁、溶接構造物に幅広く使われる、熱感圧延によって製造される「汎用鋼材」です。材料記号は『SSと3桁の数字』で表され、この数字は引張強さを元にしています。
代表例:SS400
・引張強さ:400〜510 MPa
・伸び:≧21%(板厚16mm以下の場合)
溶接性がよく、鍛造などの塑性加工を行いやすいため、建築や橋梁、溶接構造物に幅広く使われます。
(溶接性;金属材料が割れや変形を起こさずに、適切な強度を保ったまま溶接できる性質)
炭素量は規定されていないため、調質や熱処理(焼入れ+焼戻し)は行わず、多くの場合はそのまま使われます。
2. 機械構造用炭素鋼(JIS G 4051: S○○C材)
シャフトやギア、ボルトなど機械部品に多用される鋼材群です。この規格の鋼材は熱間圧延、熱間鍛造、熱間押出の製造方法で規定されています。材料記号の数字が炭素量を表しており、含有成分量で材種が規定されています。
代表例:S45C
・炭素量:42〜0.48%
よく使われるS45CやS50Cの炭素量では、調質や熱処理(焼入れ+焼戻し)を行うことで引張強さや耐摩耗性を強化できます。炭素量が多くなるほど、硬くすることができます。
SS材に比べると溶接性は劣りますが、強度と靱性を兼ね備えた機械部品に適しています。
3. みがき棒鋼用一般鋼材(JIS G 3108: SGD 〇材)
みがき棒鋼用として棒状(丸、角、六角、バーインコイル)に熱間圧延される一般鋼材です。材料記号は、『SGD』の後にアルファベットまたは数字を付けて表されます。SGDに続く記号がAもしくはBのものは機械的性質で規定されており、1から4のものは成分量で材種が規定されています。
代表例:SGD B
・引張強さ:400〜510 MPa
このSGD Bという材質を用いて製造されるみがき棒鋼(冷間引抜材)は、SGD400-Dと呼ばれます(JIS G 3123)。なお、一般的な構造用鋼であるSS材には、みがき棒鋼を製造する規定がないため、SS400の精度の良い棒材が必要な場合には、性質が似たSGD Bが使われることもあります。
(冷間引抜材は、加工硬化の影響により、熱間材よりも引張強さが高く規定されています。
SGD400-D:φ5~φ20=500〜850 MPa )
JISに規定されているみがき棒としては、前述した“機械構造用炭素鋼”や“硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材”(SUM材)、後述する“機械構造用合金鋼鋼材”などが素材として規定されています。
機械構造用合金鋼鋼材(JIS G 4053)
炭素鋼の強度や靱性では限界がある場合、クロム(Cr)、ニッケル(Ni)、モリブデン(Mo)といった元素を添加することで、構造材としての性能を高められます。これが“機械構造用合金鋼鋼材”(以下、合金鋼)であり、機械設計や金型、航空機部品など高度な要求性能に応える材料群です。
合金鋼に含まれる合金元素と効果
合金鋼に含まれる合金元素としては、主に焼き入れ性を向上させる効果がある以下の元素が挙げられます。焼き入れ性とは、焼き入れ・焼き戻し(熱処理)を施した時の硬化のしやすさを示す性質で、焼き入れ性の良い材質ではより深い部分まで硬化します。
・クロム(Cr)
耐摩耗性、耐食性の向上。焼入れ性も改善されます。
・ニッケル(Ni)
靭性や強度、耐熱性が向上します。
・モリブデン(Mo)
焼き入れ性、焼戻し抵抗(焼き戻し後におきる変形や変質のしにくさ)が向上します。
代表的な合金鋼
1. クロムモリブデン鋼、クロモリ鋼(SCM材, JIS G 4105)
例:SCM440
・成分:C 0.38〜0.43%, Cr 0.9〜1.2%, Mo 0.15〜0.3%
・特徴:炭素鋼に比べ、強度や靭性、耐摩耗性に優れています。また焼き入れ性も向上しているため、より深く硬度を入れることができます。自動車のギアや航空機部品、シャフト類に多く使用されています。
2. ニッケルクロム鋼(SNCM材, JIS G 4103)
例:SNCM439
・成分:C 0.35〜0.40%, Ni 1.6〜2.0%, Cr 0.6〜0.9%, Mo 0.15〜0.3%
・特徴:靱性が高く、耐衝撃性に優れています。航空機用ボルトや重要シャフトに使用されます。
炭素鋼と合金鋼の使い分け
炭素鋼(S45Cなど)
低コストで入手が容易な材質です。ただし、大型部品や高負荷条件では焼入れ硬化が不十分になることがあります。
合金鋼(SCM, SNCMなど)
高強度・高靱性・高耐摩耗性が求められる場面に適しています。特に厚肉や大型部品では焼入れ性が重要であるため、合金元素が威力を発揮します。
まとめ
・鉄は“ベースになる金属”、鋼は“鉄を改良、強化した合金”です。
・SS材は引張強さが規定されている一般構造用圧延鋼材です。これに対し、S○○C材は炭素をはじめとする含有成分によって規定される機械構造用炭素鋼で、代表的なS45Cなどは調質や熱処理で強化されて使われることもあります。
・合金鋼は「炭素鋼+合金元素」であり、高強度・高靱性・耐摩耗性・耐熱性などをコントロールできます。代表的な合金としてSCM材やSNCM材があり、自動車のギア部品やシャフトなどに用いられています。
当社S45C加工事例
産業機械 S45C調質材 通電用プローブ

本製品は、産業機械に使用される通電用プローブです。材質はS45C調質材を使用し、φ8からの素材より削り出ししています。先端の細い部分は......