
技術コラム
公差の基礎を解説!ものづくりの“ちょうどよさ”を考える
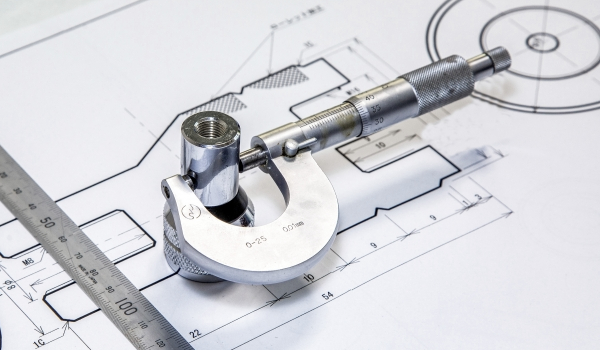
発行日:2025年11月21日
公差とは
ものづくりの現場では、「図面どおりに作る」ことが基本です。しかし実際には、温度変化や工具の摩耗、機械の精度、作業環境などの様々な影響で、寸法を完全に一致させることは不可能です。そこで必要になるのが「どのくらいのズレなら問題ないか」を定める考え方――
それが 公差(こうさ) です。
このコラムでは、サイズ公差(寸法公差)の基礎について説明していきます。
公差とは何を決めるものか
公差とは、製品の機能を満たしながら、現実的なコストで生産できるようにするための許容範囲の設定です。“悪い誤差を許す”のではなく、“使える誤差を決める”。つまり、性能とコストの最適なバランスをとるための基準なのです。もし公差がなければ、わずかな寸法差で「組めない」「ガタが出る」「音が出る」といった問題が頻発します。
しかし逆に、精度を上げるために公差を厳しくしすぎると…
・加工の工程数が増える
・温度管理が厳しくなる
・仕上げ工程が追加される
・それを保証するための測定や検査の工程数が増える
・不良が増える
など、「作る手間」だけでなく「確認する手間」も同時に増えることで、加工コストが跳ね上がり、生産が非効率になります。
この“ちょうどよい範囲”を見極めることこそが、公差設定の目的です。
なぜ許容範囲が必要なのか
例えば、長さ100.00mmのシャフトを作るとします。
もし「寸法は100.00mmぴったりでなければならない」と決めてしまうと、ほとんどの部品が不合格になります。工程数が増えることで加工時間も測定時間も何倍にも膨れあがり、工具費・設備費も大きく増えます。それでも、完璧に100.00mmに作ることは実質不可能です。
一方で、±10mmのようにゆるすぎると、必要とする機能を損なうかもしれません。
このように、公差とは「品質を守るための最小限の精度」と言えます。
どのくらいのズレなら性能に影響が出ないか――その境界を考えるのが設計者の役割です。
普通公差の考え方
図面に個別の公差を記載しない場合には、図面全体としてどの程度の誤差を許容するかを別途指示する必要があります。
この全体公差は設計者が自由に設定できますが、毎回細かく決めるのは手間がかかります。そこで便利なのが、JIS(日本工業規格)が用意している 普通公差(一般公差)B 0405-1991 です。特別な理由がなければ、この普通公差を図面全体の基準として指示することで、簡潔に公差を設定できます。
この普通公差は、必要とする精度に応じて f(精級)・m(中級)・c(粗級)・v(極粗級)の4等級 に区分されており、用途に合わせて使い分ける仕組みになっています。一般的な設計では、バランスの良い 中級(m) が採用されることが多く、特別な理由がなければこの等級が基本となります。
普通公差は、設計者が「特別な精度を求めない箇所」に利用するための便利な基準です。これを活用することで図面の記載が簡潔になり、不要に厳しい要求を避けられるため、生産性の向上にもつながります。
普通公差では足りない場合の考え方
一方で、普通公差では必要な性能を確保できない場面もあります。
たとえば――
・回転部品のはめあい(モーター軸とベアリングなど)
・摺動部(スライドガイド・ピストンなど)
・光学・センサー取付け部(位置ずれが機能に直結)
こうした部品同士を組み合わせて使用する箇所では、わずか0.01mmの違いが動作や製品寿命に影響します。
そのため、より厳しい公差を設定しなければなりません。
ただし、高精度が必要だからといって、すべての寸法を一律に厳しくするのは適切ではありません。「とりあえず±0.01mmにしておけば安心」といった安易な設定は、加工や測定の負担を増やし、結果としてコストだけが増えてしまうのです。公差は小さくするほど良いというものではなく、機能・加工・測定のバランスを踏まえて決める必要があります。
公差を“厳しくする”のではなく、「なぜその精度が必要なのか」“根拠をもって決める”ことが重要です。
そこで、普通公差だけでは対応しきれない場面で使われる公差についても、簡単に触れておきます。
部品同士を組み合わせる際に寸法の許容範囲を決める「はめあい公差」というものがあり、JIS B 0401による公差記号を使って図面に簡潔に指示できるようになっています。
また、寸法だけでは管理できない形状や姿勢などの幾何特性を規制する「幾何公差」という公差もあり、より精密な動きや組立てが求められる箇所では、これらの公差を組み合わせて精度を確保することが欠かせません。
もっと詳しく知りたい方はコチラ
公差を決める基本手順
1.部品の役割を整理する
「動く」「固定する」「回る」など、機能を明確にする。
2.どの寸法が性能に関わるかを見極める
中心距離・当たり代・クリアランスなどを重点的に検討。
3.普通公差で性能が確保できるかを確認
不足する場合のみ、個別に公差を設定。
4.加工方法・測定方法を考慮する
「作れるか」「測れるか」を両立させる。
精度とコストのバランス
先ほど述べたように、精度を上げるほど品質は良くなりますが、その分コストが上がります。逆に精度を下げると、組立てや性能で不具合が出やすくなります。
公差設定の目的は、このちょうどいいバランス点を見つけることです。
「必要なところにだけ精度をかける」
これが、設計の知恵であり、ものづくりの本質です。
まとめ
公差は、設計・加工・検査のすべてをつなぐ共通言語です。
設計者は「どこまでズレても問題ないか」を考え、加工者は「その範囲でどう作るか」を考え、検査者は「本当にその範囲に入っているか」を確かめます。こうした連携の積み重ねが、品質の安定とコストの両立を生み出します。
言い換えれば、公差とは「完璧に作ること」ではなく、「ちょうどよく作ること」を考えるための約束ごとです。
ものづくりの現場において、公差は単なる数字ではなく、知恵と工夫の結晶と言えるでしょう。
精度とコストのバランス、公差のご相談なら佐渡精密まで!
今回は、サイズ公差(寸法公差)を中心に、公差の基礎について紹介しました。
精密金属加工VA/VE技術ナビを運営する佐渡精密株式会社は、幾何公差やはめあい公差を含めた精度検討、加工方法の最適化、品質を維持しながらコストダウンを行うご提案(VA/VE)にも対応しております。
佐渡精密は1970年の創業以来、切削加工を中心に、表面処理、熱処理・研削・組立などを加えた精密金属加工のプロフェッショナルとして、様々な精密金属加工を行ってきました。お取引先では、医療機器、半導体製造装置、航空機などの、高度な技術レベルを求められる業界のお客様が多く、皆様には大変、ご満足いただいたとの声をいただいております。
公差の設定やコストダウンにお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください!





